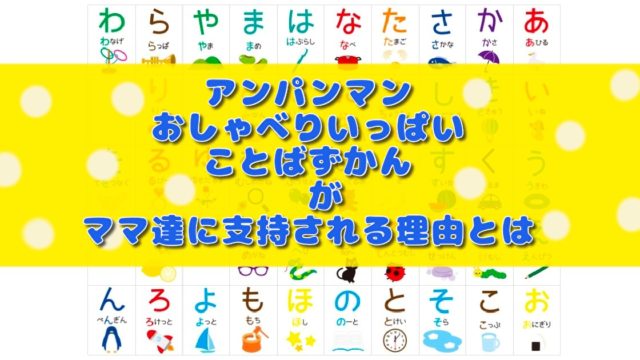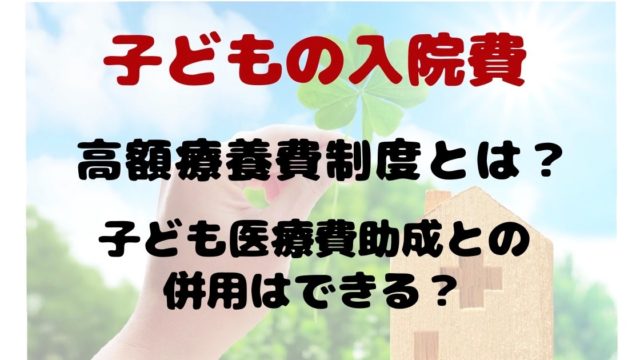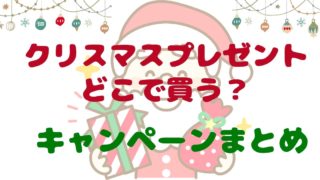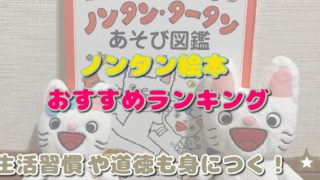世間ではコロナの第3派でGoToトラベルを中止するかどうかや、経済への影響のニュース等が飛び交っています。この記事はそのコロナ禍であまり知られることのない、小児病棟で病気と闘う赤ちゃんや子ども、付き添いママやパパの大変な現実をたくさんの人に知ってもらいたいなという気持ちで書きました。
ひよママの娘は生後3ヶ月から1歳になるまで長期入院をしていました。
その頃でさえ、心身ともに疲弊していたのに、このコロナ禍で面会等も制限され、今入院している子ども達や付き添いのご家族のことを思うと本当に頭が下がります。
まずは、「知ってもらう」ということが小さな一歩ではないかと思っています。
多くの人が大変な状況にあると思うのですが、少しでも目を向けて知ってもらうだけでも何か今後に変化があるのではと期待します。
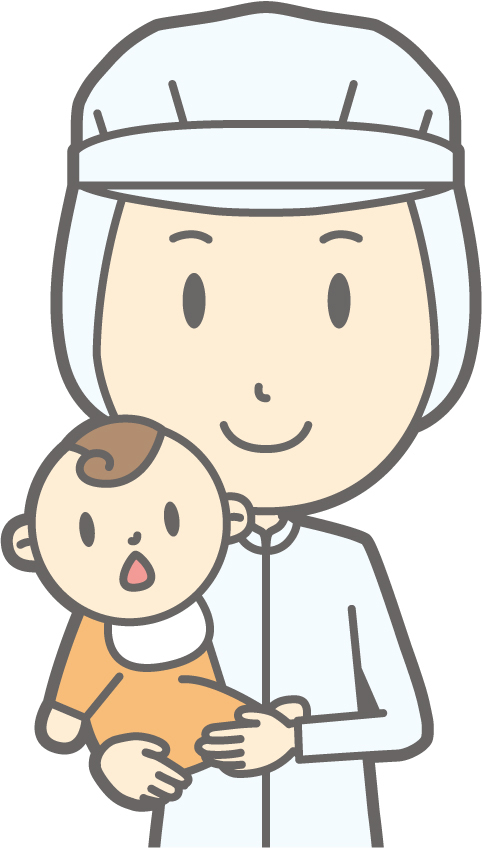
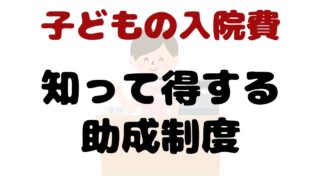
コロナで厳しくなった小児病棟のルール
小児病棟のルールは成人病棟のルールより厳しいことが多いです。
外科病棟ではなく、感染症にかかりやすい状態の子ども達が入院する病棟の場合はより厳しくなります。
白血病や小児がんの子どもが入院する病棟では、免疫機能が下がっていて、健康な人ならなんてことない菌に感染しただけで重症化するような子ども達がたくさんいます。
病院によって、細かいルールは異なりますが、面会人数の制限や15歳未満の子どもの面会の禁止があります。
このコロナ禍でさらにその面会制限は厳しくなり、面会中止、制限強化を余儀なくされています。
子どもに付き添いができない、パパに会えない、祖父母に会えない
病院によっては、子どもとの付き添い入院が認められなくなったところもあるようです。
産まれたての赤ちゃんや0歳児、いろいろなことがわかってきている1歳以上の子どもが突然ママに会えなくなったことを想像してみて下さい。
保育園でも慣らし保育をしますよね?そんな慣らしなんてものもなく、ママやパパに会えなくなってしまうのです。
病気でしんどい時こそ、傍にいてあげたいのに傍にいてあげられない親の方も辛いです。
ひよママの娘が昨年入院していた時、感染病棟という隔離部屋ばかりの病棟があったのですが、そこでは感染予防のため、付き添いが禁止されていました。
入院中にRSウイルスに娘が感染し、その感染病棟に入院するかもしれないとなった時、感染病棟に入院経験のあるママが体験談を話してくれました。
子どもは一晩中泣き続けて、胸に刺さったカテーテルを引き抜いてしまったというのです。
抗がん剤投与等に使われるカテーテルは胸等から中心静脈に挿入する管のことです。
子どもにとって突然ひとりにされ、常時看護師が付き添ってくれる訳でもない環境がどれほど心細かったことかと思います。
結局、ひよママの娘は感染病棟には入院せず、一時帰宅することにしました。
しかし、長期間入院していたことで、「病院」という場所がかなりトラウマになっているようで、検査入院の時も半日は泣き続けます。
今、コロナでママやパパが子どもに付き添いできないことで与える心身への影響が問題になっています。
小児がん患者の親が宿泊できる施設が病院の近くにあるのですが、現在は宿泊者を一人までに制限したり、外出自体を制限するケースがあります。
付き添いは途中で交代でできると、自宅に帰ることができリフレッシュできるのですが、それができないとなると健康面にも影響が出てくると思います。
面会は家族のみという制限の病院もあるので、産まれた赤ちゃんをまだ祖父母に会わせることができずにいるという状況もあるみたいです。
プレイルームの制限
ひよママの娘が入院中、あって良かったなと思ったのが、病棟内にあるプレイルームです。

プレイルームは支援センターのイメージで、おもちゃや絵本があります。病院によってはテレビゲームもありました。
このプレイルームは子どもが楽しむだけでなく、病棟内のママ達とのコミュニケーションの場にもなっていました。
ベッドと少しのスペースしかない病室に籠るだけの生活において、プレイルームはリフレッシュの場でした。
この憩いの場もコロナの影響で、時間制限や入院から数日は一切入室禁止等の措置がとられています。
ひよママの娘も12月に経過観察のため、2泊3日の入院を予定しています。入院する病院は入院から3日間はプレイルームには入れません。
病院がトラウマ化している娘の気分を唯一切り替えられるプレイルームが使用できないということなので、今からどう対策をしようか思い巡らせています。
ただでさえ、病院内から出られない子ども達が唯一楽しめるはずの場所さえも奪われてしまっている現実に、コロナをどう恨めばいいのかもわかりません。
付き添いママの食事についてもコロナの影響が
コロナの影響で様々な制限がかかっていますが、それは感染予防の観点からすると仕方のないことで、大切な措置ではあります。
白血病や小児がんの病棟に付き添い入院するママやパパは日頃から徹底して感染予防をしています。
ただの風邪さえも、命を脅かす可能性があるからです。
それでも多くの付き添いママは、病院内のコンビニで食事をとったり、病院周辺のスーパーや定食屋等で食事をしていました。
しかし、コロナの影響で、病院外での食事にも気を遣い、病院内のコンビニのイートインスペースも閉鎖されたりしていて、病室での食事を余儀なくされているケースも多くあります。
祖父母が食事を持ってきてくれても、病棟外での受け渡しになります。
唯一の息抜きの食事も病棟内でとることになっています。
半年や一年、それ以上その生活が続くとなると本当に付き添い人が体調を崩しかねないですよね。
感染者数が落ち着いていた夏頃も制限は変わっていないところが多く、一刻も早い収束が願われます。
外泊や一時退院ができない

抗がん剤投与をしていると、免疫が回復する期間は外泊や一時退院で自宅に帰れる場合があります。
ひよママの娘は基本的には2~3週間に一度、1泊から1週間程の外泊や一時退院ができていました。
その期間がなければ付き添い入院生活を続けられなかったと言えるくらい、体力的にも精神的にも救われていました。
その外泊が感染の恐れがあるためにできなくなっているケースが多くなっています。
市中感染が広がっているため、リスクが高いのでしょうがないと思うしかないのですが、子どもに数日でも普通の生活をさせてあげられないのは成長の過程としても影響が懸念されます。
1歳半頃から本当に子どもなりにいろんなことがわかってくるので、子どもの精神面も心配です。
懸念される手術等の延期
コロナ患者が急増し、病床を圧迫するとそのために医師や看護師が必要になります。コロナでは肺炎の有無を確認するため、CT検査等を行います。
大きな病院ではコロナ禍でなくても予約でいっぱいなので、今後必要な検査が延期される可能性があります。
同じく手術に関しても、テレビのニュースやワイドショーで延期になっているところがあるといいます。
ひよママの娘が小児がんであるとわかり、生検手術をすることになった時、土日や祝日を挟むため、すぐに手術ができなかったことがあります。
もちろん、お医者さんにも休みは必要なのですが、一刻を争うかもしれないのに、土日を待ってられるかと思った経験があります。
コロナの影響で他の病気で必要な手術が延期になったり、コロナ患者の方も含めて、受けられるはずの医療が受けられなくなることがないように願うばかりです。
広がるクラウドファンディング
コロナ前にも、小児病棟を子どもがわくわくするような内装にするための改装費用のクラウドファンディングや、風船を届けるためのクラウドファンディング等たくさんの支援の輪が広がっていました。
現在、大阪大学医学部附属病院では、とても素敵なクラウドファンディングが行われています。
コロナ禍による厳しい面会制限によって、生まれてから一度も赤ちゃんに会うことのできないご両親のために、また家族と僅かな時間しか会えない小児病棟入院中のお子さんのために、24時間、どこからでもオンライン面会ができるシステムを構築することを目指し、1000 万円を目標としたクラウドファンディングを9 月14 日(月)から開始します。
<READYFORより引用>
既に3000万円を上回る寄付金が集まっています。
このような頑張っている赤ちゃん、子どもたちのためにできることがネットにも溢れています。
まとめ
子どもが病気になってしまうことは誰のせいでも責任でもありません。感染症が起こっても誰を責めればいいのかもわかりません。
どんな環境であっても、ひたむきに頑張り、無垢な笑顔を見せる子ども達がどうかこれ以上苦しめられないようにコロナの収束を願います。
普段生活していると、小さい子どもが闘病していたり、付き添う家族がどんな生活をしているのかの情報は入ってこないと思います。
ひよママも実際に娘が入院してみて、初めて小児の医療現場を目にしました。
どうしてこれまで何も目を向けてこなかったんだろう、どうしてもっと献血に行かなかったんだろう、募金をしなかったんだろう、ボランティアに参加しなかったんだろう・・といろいろな後悔をしました。
家族でお風呂に入ったり、食事をしたり、公園に出かけられることが当たり前じゃない、とっても恵まれた幸せなんだということに気付きました。
病院の外に出られない子ども達が、病棟内の憩いの場や会いたい人にも会えない状況で頑張っているんだということを少しでも知ってもらえたらいいなと思います。